知っておきたい
介護保険制度の基礎知識
|
「介護保険制度」とは、年老いて寝たきりや痴呆になったとき、誰もが安心して、容易に介護がうけられるように、40才以上の人が全員でその費用を負担し、未来の不安や負担を解消するためにつくられた制度で、2000年4月より実施されています。
この「介護保険制度」のしくみを簡単にご紹介します。
|
| |
 介護保険加入者は 介護保険加入者は |
40才以上の人が対象となります。65才以上の人{第1号被保険者}と、40才〜64才の人{第2号被保険者}があり、それぞれ保険料の支払いが違っています。
|
| |
 介護サービスを利用するには 介護サービスを利用するには |
まず、要介護認定の請求を行い、「介護が必要かどうか」を認定してもらいます。自分が住んでいる市町村の福祉担当窓口や在宅支援センター、訪問看護ステーションなど介護支援専門員{ケアマネージャー}のいるところでも申請の代行をしてもらえます。本人が申請できないときは、家族の方でもかまいません。
|
| |
 |
要介護認定とは |
| 「介護が必要である」と認められて、初めて介護サービスが受けられます。この判定を要介護認定といいます。面接調査の結果と主治医の意見書をもとに、複数の専門家による「介護認定審査会」にて、その方がどのくらいの介護を必要としているかが判定されます。要支援から要介護1〜5までの6段階があり、その段階ごとに介護保険で利用できる金額が決められています。 |
|
| |
 申請から認定までの流れ 申請から認定までの流れ |
 1.訪問調査 1.訪問調査 |
| 申請を行うと、市町村の職員か介護支援専門員が自宅を訪れ、食事、入浴、排泄などがどの程度できるかを面接調査します。それとともに、かかりつけの医師から障害の原因やケガ、病気についての意見書を書いてもらいます。 |
| |
 2.審査判定 2.審査判定 |
| 介護が必要かどうか、どの程度の介護サービスが妥当かを市町村に設置された「介護認定審査会」が判断されます。その際には、面接結果とかかりつけの医者の意見書が参考にされます。認定結果は申請から30日以内に文章で通知されます。 |
| |
 3.サービスの利用 3.サービスの利用 |
| 認定されたらサービスの種類を選びます。介護保険では、保健・医療・福祉の様々なサービスが総合的に用意されています。利用する方の生活スタイルに応じて選びましょう。上手な利用のためのアドバイスを専門家{介護支援専門員:ケアマネージャー}から無料で受けることができます。もちろん、自分で介護サービスの利用計画を作ってもかまいません。 |
| |
 介護サービスの利用料 介護サービスの利用料 |
| 介護保険の利用料の1割は自己負担です。介護サービスを利用した場合、利用者は利用料の1割をサービス提供事業者に支払います。介護サービスは要介護度に応じて利用限度額が決められています。各要介護度の限度額を越えてサービスを利用した場合は、限度額を超えた金額分は自己負担となります。 |
| |
 介護サービスの種類 介護サービスの種類 |
| 介護サービスは「在宅サービス」と「施設サービス」に大別できます。「要介護」と認定された人はどちらの介護サービスも受けられますが、「要支援」と認定された人は、「施設サービス」は利用できません。 |
| |
 主なサービス 主なサービス |
 訪問介護 訪問介護 |
| ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護を支援。 |
| |
 訪問入浴 訪問入浴 |
| 入浴チームが家庭を訪問し、入浴を介助。 |
| |
 訪問看護 訪問看護 |
| 看護師などが家庭訪問し、必要な看護を実施。 |
| |
 訪問や通所によるリハビリテーション 訪問や通所によるリハビリテーション |
| 専門家の家庭訪問や施設でのリハビリ指導を実施。 |
| |
 居宅療養管理指導 居宅療養管理指導 |
| 医師などが家庭訪問し、療養上の管理や指導を実施。 |
| |
 通所介護{ディサービス} 通所介護{ディサービス} |
| ディーサービスセンターなどに通って、入浴や食事、機能訓練などを実施。 |
| |
 短期入所サービス{ショートステイ} 短期入所サービス{ショートステイ} |
| 老人ホームや老人保健施設などでの短期入所。 |
| |
 痴呆対応型共同生活介護{グループホーム} 痴呆対応型共同生活介護{グループホーム} |
| 痴呆状態にある要介護者が10人位で共同生活を営む施設{グループホーム}での介護。 |
| |
 有料老人ホームなどにおける介護 有料老人ホームなどにおける介護 |
| 有料老人ホームでの介護。 |
| |
 福祉用具の貸与や購入の支給 福祉用具の貸与や購入の支給 |
| 車椅子や介護ベッドなどの貸与や特殊尿器などの購入費支給。 |
| |
 住宅改修費の支給 住宅改修費の支給 |
| 手すりの取り付け、段差解消など、小規模な改修費用の支給。 |
| |
 居宅サービス計画{ケアプラン}の作成 居宅サービス計画{ケアプラン}の作成 |
| 介護サービスの内容の相談・計画。および、計画が確実に提供されるように介護サービス提供事業者などとの連絡調整。 |
| |






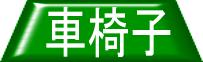






















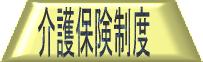








 /
/

